お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
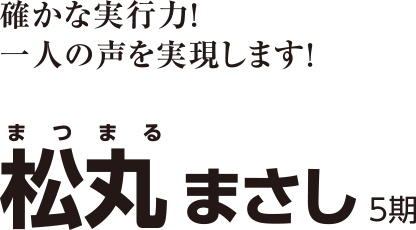
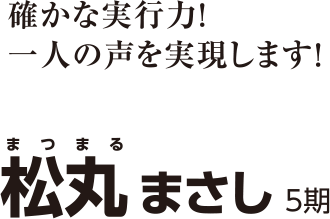
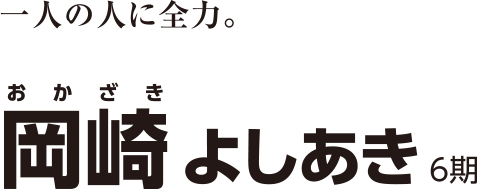

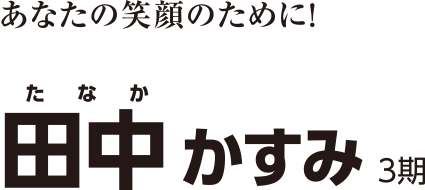
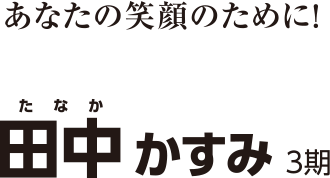


![]()
![]() 質問
質問
次に、災害対策の更なる強化についてお伺いします。
能登半島地震から約11ヶ月となります。この間、この災害現場でのさまざまな教訓を生かし、国や都、そして、区でも更なる災害対策の強化を進めてきました、
区では、「緊急防災対策事業」を、スピード感をもって組み立て、6月補正予算にて可決し、3つの事業をスタートしたこと高く評価します。
災害時のトイレ対策については、緊急防災対策事業にも特に重要な視点として盛り込み、取り組んでいます。
国においては、各自治体での「災害時におけるトイレ確保・管理計画」の策定を促してきましたが、東京都は能登半島地震の教訓を受けて今年度の策定を進めています。この計画策定には区市町村の取組を支援していくこととしていますが、本区においても「災害時におけるトイレ確保・管理計画」の策定の検討が必要かと考えますが、区の見解をお伺いします。
また、上下水道の耐震化も重要な課題です。
国交省は本年11月1日、上下水道施設の耐震化状況に関する緊急点検の結果を公表しました。
調査結果では、避難所や病院など災害時に拠点となる「重要施設」のうち、施設につながる管路が上下水道とも耐震化されている施設の割合は東京都で52%となっていて、上水道では91%、下水道では81%、重要施設につながる下水道にあるポンプ場の耐震化率は81%となっています。国交省では、「今後、耐震化計画に基づき、地域の取組を技術的・財政的に支援していく」としています。引き続き、都と連携を図り、上下水道の耐震化を力強く進めていくべきと考えますが、区の見解をお伺いします。
このテーマの最後にペットの同行避難についてお伺いします。
地域では、朝夕を中心に犬の散歩をしている方々をよくお見かけするようになりました。
災害時においては、ペットの同行避難を心配するお声もありますが、自宅が安全であれば在宅避難をすることが一番安心です。一方で、在宅避難が難しい場合の対応が課題となります。能登半島地震では、ペットを一時的に預かるNPO法人が活躍されていたとの報道がありました。この法人は2016年の熊本地震以来、各地の災害現場で犬や猫を預かる活動をして、石川県珠洲市でも本年2月中旬から「わんにゃんデイケアハウス珠洲」の運営を開始しています。運営スタッフのコメントとして、「行政が行き届かないペットの支援を民間がカバーしなければ」と紹介され、今後も活動を継続するとのことです。本区においても、災害時のペット同行避難のあり方や、一時預かりの可能性を探るため、こうした民間団体との協働を検討してはいかがでしょうか、区の見解をお伺いします。
|
区長 |
次に、災害対策に関するご質問にお答えします。 まず、災害時のトイレ確保・管理計画についてのお尋ねですが、 区としても、災害時の避難生活に欠かせないトイレ対策は、重要な課題の一つと認識しております。そのため、避難所における携帯トイレの備蓄の拡充を図るほか、公共施設の改築等の機会を捉え、マンホールトイレ等の整備に取り組んでおります。 現在、都において、「災害時トイレの環境向上策」の検討が進められており、予防・応急・復旧フェーズに応じた対応策や区市町村との連携等について検討されているところです。 区においては、今後も、地域防災計画に基づき、災害時におけるトイレの確保に取り組んでまいりますが、災害時トイレの個別計画の必要性については、都における検討状況を踏まえ、研究してまいります。 次に、上下水道等の耐震化についてのお尋ねですが、 避難所等の重要施設につながる上下水道等の耐震化は、管理者である都から、計画的に実施していると聞いております。 今後とも、都との定期的な会議をはじめ様々な機会を捉え、各施設の耐震化促進に向け連携してまいります。 次に、ペットの同行避難についてのお尋ねですが、 現在、区では、ホームページや避難所総合訓練等において、ペットの同行避難について周知するとともに、避難所での生活も想定した日頃からのしつけについて、啓発に取り組んでおります。 ペットの同行避難については、それぞれのペットの状況に即した環境整備や飼い主の理解促進等、多くの課題があるため、今後、避難所運営ガイドラインを見直す中で、避難所でのルールを改めて整理してまいります。また、民間団体との協働による一時預かりについては、今後の研究課題とさせていただきます。 なお、避難所にペットと同行避難する場合、ペットは、飼い主の避難スペースとは別の場所となり、双方にストレスが見込まれるため、被災後に、ペットと生活するためにも、引き続き、在宅避難の推進に取り組んでまいります。 |
|---|