お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
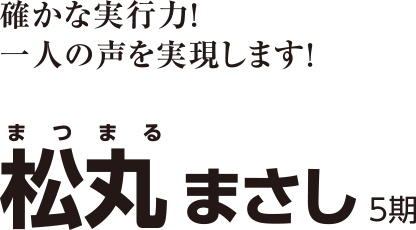
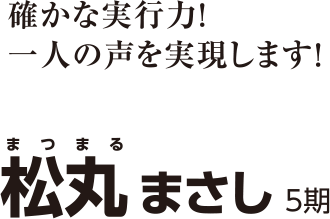
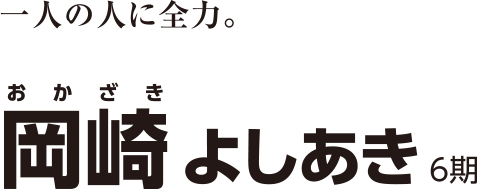

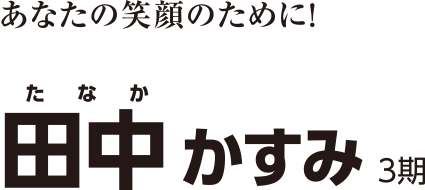
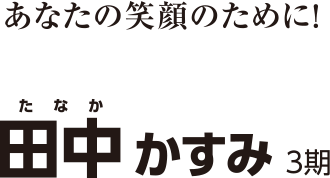


![]()
![]() 質問
質問
次に多文化共生社会の構築についてお伺いいたします。
コロナ禍で一度減少した区内の在住外国人人口は、令和4年11月に12,000人を超え、令和6年10月現在、15,469人となっており、今後も増加傾向になることが予測されます。
本区としては、多文化共生事業として、全ての人が、国籍、民族等の互いの文化的違いを認め合い尊重しながら共に生きていくことができるよう、多文化共生に向けた理解の促進に取り組んでいますが、昨今、様々な問題が地域や学校現場で起きております。本区としてどのように認識をされ、どのような改善に取り組まれているのかお伺いいたします。
文京区民と外国人が互いに尊重する共生社会への一歩として、外国人が安心して暮らせる環境の整備も必要かと思われます。
法務省は、日本に住む外国人が抱える生活上の困り事といった相談に応じ、適切な支援へとつなぐ専門家「外国人支援コーディネーター」の養成研修を始めました。コーディネーターには複雑な相談内容を解決に導く能力に加え、異なる文化や価値観を理解する能力が求められます。ただ、多くの外国人は、自治体など公的機関には相談していない現状があり、政府の調査によると、その理由として「相談できる部署や窓口がどこにあるか分からない」が最多を占めているそうです。そこで、本区として「外国人支援コーディネーター」の活用と外国人専用の相談窓口の設置をしてはいかがでしょうか。そしてその周知に一層取り組んでいただきたいと思いますがご見解をお伺いいたします。
群馬県大泉町では、「多文化共生懇談会」を年に10回ほど実施し、職員が出向いて、外国人に生活のルールや防災情報などを共有する懇談会で、特に一番の課題とされていた「ごみの問題」も分別の方法など丁寧に説明することによって課題解決に向けて進んでいるそうです。
また、長野県松本市では、2021年から地域と外国人住民の“橋渡し役”を担う人材を登録する「多文化共生キーパーソン事業」を実施し、市からの情報提供や相談事業、国際交流などのイベントへの参加など外国人住民との交流が深まっているそうであります。
本区として、多文化共生社会の構築に向けて具体的な取り組みが必要かと思われますがご見解をお伺いいたします。
|
区長 |
次に、多文化共生社会の構築についてのご質問にお答えします。 昨今、外国人住民が急増していることを受け、文化の違いなどによる住民同士のトラブルに発展しかねないような苦情や相談が寄せられているところです。 区では、こうした状況を踏まえ、多文化共生連絡会を開催し、地域や学校現場における課題を共有するとともに、必要な対策を速やかに講じていくことを確認しております。 また、外国人専用の相談窓口の設置については、現在のところ予定しておりませんが、「外国人支援コーディネーター」は、外国人が安心して暮らせる環境の整備に効果的であると考えられることから、他自治体の事例も参考に、活用等について研究してまいります。 区としては、今後とも、生活実態や課題等についての把握に努め、外国人との共生社会の構築に向けた取り組みを推進してまいります。 |
|---|