お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
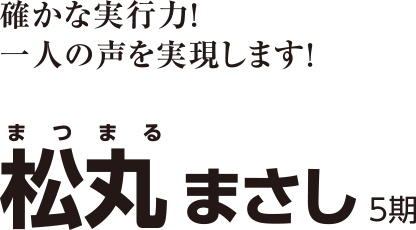
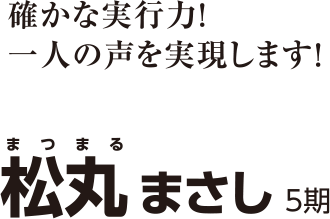
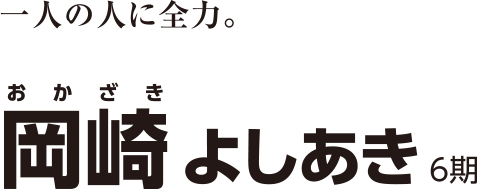

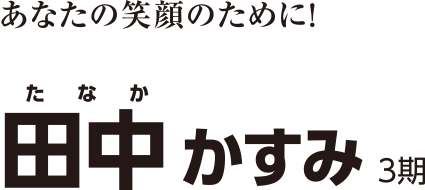
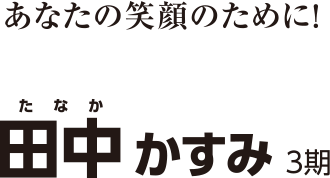


![]()
![]() 質問
質問
次に、若者孤独死についてお伺いします。
今、若者の間でも誰にもみとられずに亡くなる「孤独死」の深刻化が危惧されております。誰にもみとられずに一人暮らしの自宅で亡くなる「孤独死」をした10代~30代の若者が、平成30年から令和2年の3年間に東京23区で742人確認され、うち約4割が死亡から発見までに4日間以上を要していたことが東京監察医務院での報告で分かりました。
孤独死をめぐっては高齢者が社会問題化しておりますが、今回の監察医務院の統計からは、若者も長期間、発見されないなど、深刻化している実態が浮かんでいます。高齢者も含め孤独死につながる要因は、経済的困窮や認知症など多岐にわたり、生活を維持する意欲や能力を失う「セルフネグレクト」も背景にあると言われていますが、外部との関りも断ってしまうなど実態が顕在化しにくいものも実情とのことです。
令和5年版厚生労働白書によると、セルフネグレクト(自己放任)とは、不衛生な環境での生活や必要な医療・介護サービスを拒否するなどし、心身の健康維持ができない状態を指し、背景に認知症や疾患、経済的困窮、人間関係のトラブルなどが挙げられ、孤立死との関連が指摘されているとのことです。ニッセイ基礎研究所の平成23年の調査によると分析した孤立死事例の約80%が「セルフネグレクト」に至る大きなリスクを負う状態と示されました。
東邦大看護学部・岸恵美子教授は「これまでセルフネグレクトは高齢者の問題と捉えてきたが、若者に照準を合わせなければいけない。その上で現状、国は既存の制度の対象になりにくい事例も、包括的に対応する重層的支援体制整備事業でセルフネグレクトに対応する方向であります。ただ、相談対応だけでは命や人権に関わる深刻な事例が起こりえる。定義が不明確なため自治体の調査にもばらつきがあり、法制度化しないと命を救えない。」と指摘しております。
本年4月に孤独・孤立対策推進法が施行されてから半年となります。孤独・孤立の問題を「社会全体の問題」と位置付け、世代を超えて蔓延し深刻化するこの問題に、対策を講じていかなければなりません。本区の見解をお伺いします。
|
区長 |
最後に、若者をはじめとする孤独・孤立の課題についてのご質問にお答えします。 本区では、支援が必要な方の状況に応じて、子ども、高齢、障害、生活困窮及び保健・医療の支援に係る相談支援機関等との連携を強化し対応しております。 また、社会福祉協議会を通じて多機能な居場所づくりを進めており、孤独・孤立を予防する観点からも、一人で抱え込むこと、悩みや困りごとの複雑化・深刻化を防ぐため、日常にある「つながり」が有効になると考えております。 今後は、重層的支援体制整備事業を活用し、各支援機関が協力して支援を担うチーム体制を構築するとともに、必要に応じて専門職につながる地域ネットワークづくりの場を整え、若者をはじめとする孤独・孤立の状況にある人を取り残さない地域づくりを目指してまいります。 |
|---|