お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
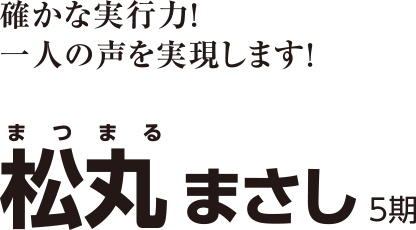
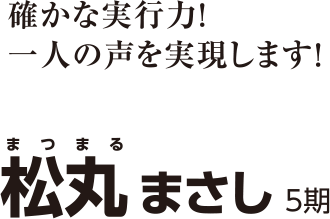
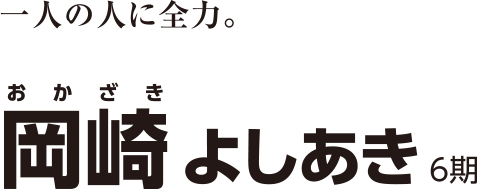

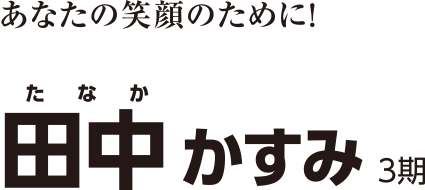
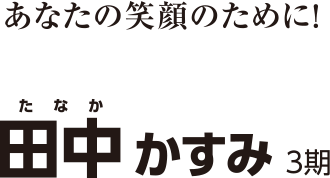


![]()
![]() 質問
質問
最後に学校へ登校できない、教室に入れない児童生徒への支援と、保護者のサポート強化について伺います。
全国では不登校の小中学生が2023年度は34万6482人に上り、過去最多となったことが文部科学省の調査でわかりました。前年度比4万7434人(15・9%)増で、初めて30万人を超えたことになります。
本区においても増加傾向ですが、重要なのは、児童生徒の教育活動を保障すること、そして、「我が子が不登校になった。進学はできるだろうか」また「我が子が不登校なったらどうなってしまうんだろう」という保護者の不安を支えることです。
こうした親子にあたたかく寄り添い道を開いていただきたいです。不登校児童生徒、保護者に対する支援について、今後どのように進めていくご決意か、初めに伺います。
不登校児童生徒の支援として令和6年度の重点施策「学びの架け橋プロジェクト計画」では、校内居場所を小学校6校、中学校6校に設置しました。教室には行けないが、校内別室で支援員や友人と過ごすなど、学校に登校し、教育活動の継続に繋がった児童生徒は、今日まで何人になりましたでしょうか、また、校内に居場所を作った効果をどのように捉えているでしょうかお伺いします。
学校が希望しているのに設置できていない、または設置しているが、支援員が不足していて短時間しか居場所にいられない、など課題を抱えている学校の要望を早急に解決する必要があります。具体的にどのように進めていくのか区の見解を伺います。
また、別室での活動内容の充実が必要と考えます。
今年度、民間フリースクールが実施するソーシャルスキルトレーニング講座やオンライン授業を受講できるようにするとのことですが、ふれあい教室のみでの取組となっています。この取組を、別室利用の児童生徒にも拡充することが有効かと思いますがいかがでしょうか、区の見解を伺います。
次に保護者支援についてです。我が会派が提案した、各学校単位ではなく文京区が主催する進路相談会や保護者会、保護者同士交流する場づくりを作っていただき、保護者から「不登校になっても思った以上に選択肢があって驚いた」「皆さんの話が参考になった」「心が軽くなった」などの声を伺っています。今後も、保護者同士の交流会や、体験談などを共有する場などを拡充していく必要があると思いますが、区の見解をお伺いします。
最後に、コーディネーターの配置について伺います。
学校や学校以外の関係機関に相談せず、または相談先がわからず、適切な支援が届かないケースがあります。こども家庭庁は、学校だけでなく、地域全体で不登校の子どもを支援する仕組みが必要と判断し、来年度、地域一体で不登校の子どもを支援する体制をつくるため、約20自治体でモデル事業に取り組むとしています。子どもや保護者からの相談を受け、関係機関につなぐ役割を果たすコーディネーターを配置し、子どもの社会とのつながりを持つための支援も行うものです。
コーディネーターは、医療機関やフリースクールなどで不登校支援に長く携わった経験を持つ人を想定するとのことで、モデル事業では、1自治体当たり1000万円程度を上限に補助する見通しです。専門的な知見を持ち合わせたコーディネーターであればこそ、学校に行けない児童生徒の進路の不安や、保護者の心配にもより広いアドバイスができ、相談内容に応じて医療・福祉機関の紹介や、民間のフリースクール等のマッチングを行うことができます。本区でのコーディネーターの配置を提案しますが、区の見解を伺います。
以上で質問を終わります。ご清聴、誠に有難うございました。
|
教育長 |
はじめに、不登校の児童・生徒、保護者に対する支援についてのお尋ねですが、 不登校の児童・生徒数が増加し、その背景も複雑化・多様化する中においては、不登校の児童・生徒への支援はもちろん、その保護者への支援の必要性を強く感じております。 また、そうした支援や不登校が生じない魅力ある学校づくりの実現のために、学校と教育センター等が連携・協力し、「チームとしての学校」をつくり上げ、組織的に取り組むことが必要だと考えます。 そこで、教育センターでは、引き続き、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの学校への配置を行ってまいります。こうした職員が、早期に学校で気になる子どもの様子を教員と共有し、個々に必要な心のケアや福祉的な支援に向けた調整に取り組んでまいります。 あわせて、不登校児童・生徒の保護者を対象とした進路説明会の開催等により、保護者支援にも取り組んでまいります。 次に、「学びの居場所架け橋計画」の効果等についてのお尋ねですが、 本年度の校内居場所の利用者は、10月末現在、126名です。 成果といたしましては、校内に別室があることで児童・生徒が登校しやすくなり、学校とのつながりを維持できるだけでなく、別室利用から教室に復帰できるようになるなど、不登校の未然防止及び早期対応に一定の効果があったものと捉えております。 次に、「学びの居場所架け橋計画」の課題への取組についてのお尋ねですが、 校内居場所対応指導員の配置校は、本年11月に、2校拡充し、小・中学校合わせて14校としました。 そして、令和7年度は、さらに6校拡充し、20校に配置する予定です。 校内居場所対応指導員を配置している学校においては、指導員を中心に、状況に応じて教職員やスクールカウンセラーなどが指導員を支援しながら子どもたちに対応してまいります。 また、指導員を配置していない学校においては、スクールカウンセラー等に加え、家庭と子供の支援員を活用して、教職員と連携しながら子どもたち一人一人の支援に取り組んでまいります。 次に、校内居場所での活動内容の充実についてのお尋ねですが、 現在、各校ではそれぞれの実状に応じて校内居場所の運営をしております。まずは、校内居場所対応指導員を配置しているモデル校での先進的な取組をはじめ、各校の取組を全区立小・中学校で共有することにより、活動内容の充実を図ってまいります。 なお、民間フリースクールの講座等については、引き続きふれあい教室で活用し、校内居場所での活用は研究課題とさせていただきます。 次に、不登校児童・生徒の保護者への支援についてのお尋ねですが、 本年度は、6月に、主に中学校3年生の保護者を対象とした進路説明会、11月に、主に小学生から中学校2年生の保護者を対象とした進路説明会を開催しました。 6月の参加者は37名、11月の参加者は26名でした。 この他、不登校児童・生徒の保護者への支援に係る取組として、ふれあい教室の保護者会において、不登校を経験した人の体験談を聞く機会を設けました。あわせて、総合相談室を利用中の保護者を対象に、「不登校・登校しぶりを考える保護者の集い」を今後実施する予定です。 今後も、こうした取組を充実させることにより、保護者への支援に力を入れてまいります。 最後に、議員ご提案の「コーディネーター」の配置についてのお尋ねですが、 本年度からスクールソーシャルワーカーについては、週1日配置する学校を10校拡大し、全区立小・中学校に配置しております。 配置したスクールソーシャルワーカーが、保護者の負担や懸念を丁寧に聞き取り、必要に応じて地域の居場所や支援機関のほか、関係機関に繋げております。 本区では、引き続き、スクールソーシャルワーカーの活動の充実により、ご指摘のようなニーズに対応してまいります。 なお、「コーディネーター」の配置については、国の動向を注視してまいります。 |
|---|