お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
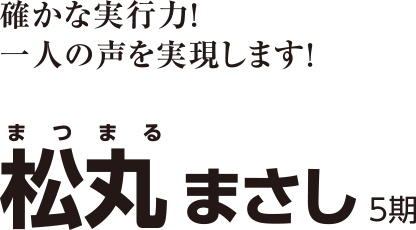
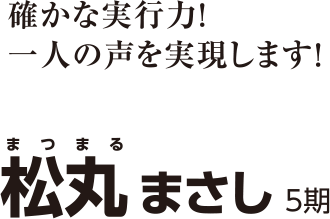
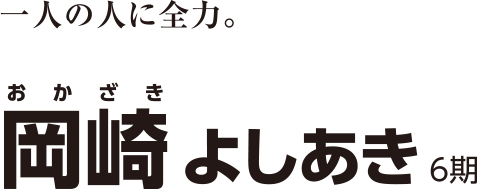

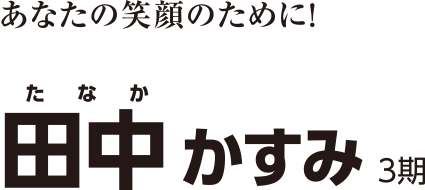
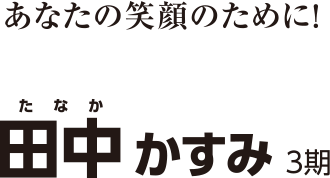


![]()
![]() 質問
質問
次に、外国人との共生社会についてお伺いします。
2025年1月1日現在の文京区の人口総数23万5345人で、うち外国人住民は1万5923人で人口比率は約7%となります。
2020年1月1日の人口と比較すると、総数は22万6114人、うち外国人住民は1万1635人で、総数の伸び率は約4%で、外国人住民の伸び率は約36%となります。
増えた人口総数の約46%を外国人住民が占めています。
2019年6月の本会議一般質問でも、10年前の人口と比較したとき、外国住民の増加率が大変に大きいことを指摘し、外国人との共生社会を目指した提案もしました。
これらの数字から言えるのは、外国人住民の増加率が引き続き大きいことと、人口増加総数に占める外国人の比率が大きくなっていることです。
本区では、「文の京総合戦略」の中でも、多文化共生社会を目指すことと明記していますが、我が会派に寄せられるお声では、外国人とのトラブルを心配する意見が断続的に続いており、昨年11月定例議会での本会議一般質問でも取り上げ、多文化共生社会構築に向けた提案もしました。
最近では特に、中国人住民が急増しているようです。現在の外国人住民の出身国別の人数をお伺いします。
こうした中、先日、文京区日本中国友好協会の会長からも我が会派に心配の言葉が寄せられ、出来ることがあればお手伝いしたいとのお申し出もありました。
まず早急に手を打つべきは、区立小学校での対応強化と考えます。
日本語ができないまま転入する児童も多く、教育委員会としても日本語指導協力員を配置してきましたが、成り手不足の状況ともお伺いしました。実態をお伺いします。また、実際に指導をして頂いている協力員からのご意見では、児童への個別指導のため、個別の資料作成が必要であることや、児童の急な欠席により仕事がキャンセルになることもあるなど課題も出てきているそうです。こうした課題解決も必要と考えますが、区の見解をお伺いします。
日中友好協会などの民間団体や、区内大学に通う留学生などに協力を要請することも有効と思いますがいかがでしょうか、区の見解をお伺いします。
次に、こうした外国人児童の保護者への対応についてです。
我が会派からもこれまでも「外国人住民向け相談窓口」の設置など先進自治体の取り組みを提案してきました。三重県桑名市では、昨年6月から「外国人支援コンシェルジュ」を市役所に置き、多言語で相談できる体制をつくり、利用者も1000人を超えるなど好評とのことです。転入してまもない外国人にはオリエンテーションを実施。ごみ分別や防災、日本語教室など生活するために必要な情報を伝えています。今後の具体的取り組みについて、区の見解をお伺いします。
|
区長 |
次に、外国人との共生社会に関するご質問にお答えします。 まず、外国人人口についてのお尋ねですが、 令和7年1月1日現在、本区において500人以上の住民登録がある国・地域は、人口の多い順に、中国8,666人、韓国1,657人、ミャンマー736人、台湾692人、ベトナム602人となっております。 日本語指導協力員の現状と課題についてのお尋ねですが、 現在、学校より教育委員会に申請があった日本語指導が必要な児童・生徒については、全ての児童・生徒に対し、日本語指導協力員を派遣しております。しかし、日本語指導協力員は長期的な雇用が難しく、常に募集をかけなければならない状況にあります。 また、転入学してくる児童・生徒の母語に対応できる人材を確保していくことが課題ととらえており、人材の確保に向けて、区ホームページ等における募集や近隣大学への協力要請等に努めております。 次に、議員ご指摘の課題の解決に向けては、既存の日本語指導教材の活用や欠席時における事前連絡の徹底など、各学校への周知に努めてまいります。 また、現在、区内大学や文京区日本中国友好協会等に協力をいただいておりますが、今後は、公益財団法人アジア学生文化協会、公益財団法人日中友好会館日中学院とも連携を図り、児童・生徒の日本語をサポートする事業の実施を検討してまいります。 次に、外国人住民に対する区の取り組みについてのお尋ねですが、 区では、一部窓口に音声文字化・多言語翻訳機能を有する透明ディスプレイを設置しているほか、ごみと資源の排出について、外国の方にも分かりやすい指導・啓発に繋がるよう、来年度から、担当する職員が多言語対応の翻訳機を携帯することなどにより、様々な現場で生活に必要な支援が行えるよう取り組みを進めているところです。 また、一部の町会では、多文化共生の意識を醸成するためのチラシの作成や、外国人住民も参加しやすいよう配慮したイベントを実施するなどの取り組みも行われるようになっており、区としても、引き続き多文化共生の理解促進に努め、あらゆる方にとって暮らしやすいまちづくりに取り組んでまいります。 |
|---|